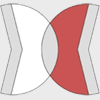
-
世界をつなぐ越境者
~Beyond the hill today, Beyond yourself tomorrow~日吉ケ丘高等学校
普通科(進学型単位制)
〒605-0000 京都市東山区今熊野悲田院山町5-22[MAPを見る]
TEL. 075-561-4142 FAX. 075-551-9046
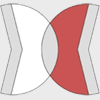
世界をつなぐ越境者
~Beyond the hill today, Beyond yourself tomorrow~
普通科(進学型単位制)
〒605-0000 京都市東山区今熊野悲田院山町5-22[MAPを見る]
TEL. 075-561-4142 FAX. 075-551-9046
厳しい寒さもようやく緩みはじめ、春の足音も聞こえてくるこのよき日に、京都市立日吉ケ丘高等学校第76回「卒業証書授与式」を挙行するにあたり、多数の御来賓、保護者の皆様方の御臨席を賜りまして、心からお礼申し上げます。
ただいま、3年次生232名に卒業証書を授与いたしました。
卒業生の皆さん、御卒業おめでとうございます。3年間の高校生活を終え、本校を巣立ってゆく皆さんに心からお祝いを申し上げます。
皆さんは、本校が進学型単位制普通科高校のグローバルコミュニケーションコース1コースとして新たな一歩を踏み出した1期生として、3年間本校で過ごしました。
一つ上の先輩と異なり、様々なことが初めての学年でした。高等学校学習指導要領が新しくなった最初の年度として、新しい科目を履修したり、自分で英語の到達目標に応じたグループA,Bを選択したり、進路を見据えたクラスの選択を行ったり、コロナ明け5年ぶりに実施となった研修旅行の行き先も自ら決定したりするなど、選択の連続だったと思います。そして、大学入試も大きく変わり、共通テストの形式も変更になりました。
このように初めてのことばかりの学年でしたが、卒業生の皆さんは、毎日の授業、文化祭などの学校行事、研修旅行、部活動、そして友だちとの日々の生活など、本校で大いに学び、かけがえのない経験ができたのではないかと思います。
さて、皆さんは、新しい5000円札の顔となっている津田梅子という女性をご存じでしょうか。彼女が生まれたのは1864年。今から160年程前、日本が幕末から明治へと変わろうとしていた時代です。それまでの日本は鎖国を続け、海外との交流をほとんど持っていませんでした。しかし、明治維新によって国が開かれると、政府は欧米諸国に追いつくために留学生を派遣し、知識や技術の導入を進めていました。
津田梅子はわずか6歳のときに、日本で最初の女子留学生の一人として、アメリカに渡りました。今でこそ飛行機なら十数時間でアメリカに行けますが、当時は、蒸気船で1か月近くかけて太平洋を横断、船酔いや食事の問題、不安定な天候など多くの困難を乗り越えなければなりませんでした。サンフランシスコに到着してからも、大陸横断鉄道に乗り、まだ開拓の途中だった広大なアメリカ大陸を、何日もかけて東へ進みました。目的地のワシントンDCに到着したのは、日本を出てから2か月近くが経過していました。
アメリカに到着した津田梅子は新しい環境に戸惑いながらも、アメリカ人家庭で育てられ、持ち前の好奇心と向上心で英語を学び、現地の学校で学びを深めます。日本最初の女子の国費留学生という使命感を胸に、現地で高等学校を卒業しました。そして、1882年、11年間にわたる留学生活を終え、17歳で帰国しました。しかし帰国後の彼女には、留学前に期待されていたような待遇はありませんでした。同じく留学した男性には政府の重要な職が与えられる一方、女性には仕事すら与えられなかったのです。
それでも数年後にやっと、女子学生を教える職につくことができました。しかし当時の日本社会における女性の地位の低さや自由のなさは、梅子がアメリカで経験したものとは程遠いものでした。そして、日本における女子教育の必要性を痛感します。同時に自分をもっと向上させるためにも、「大学でさらに学びそれを日本で生かしたい」と考え、24歳で、再びアメリカに渡り大学で学ぶことを決意します。簡単に留学と言いますが、これは明治時代のことです。しかも今度の留学は国の政策ではなく、彼女自身の強い意思によるものでした。梅子はアメリカの知人の協力を得て奨学金を獲得し、さらに当時勤務していた学校と交渉し、休職扱いでの留学を可能にするなど、主体的に道を切り開きました。多くの人に手紙を書き、熱意を伝え、支援を求めました。その結果多くの人が彼女を応援し、彼女は自らの未来を自分の手で切り開いていったのです。
そして帰国後は、女子教育のための学校を設立し、日本の女子教育の発展に生涯をささげることになります。
彼女の人生から二つ皆さんにメッセージを送りたいと思います。
一つは、「越境」の力についてです。津田梅子の生涯は、未知の世界に飛び込み、文化や価値観の違いを受け止め、自分の理想を形にしていくための挑戦の連続だったとも言えます。梅子の越境は、その当時、誰も経験のなかった海外への留学、つまり物理的な越境だけでも驚異的なことですが、それ以上に越境したことによって女性の地位向上の必要性に気づくなど、価値観の越境もあります。そして実際に女子教育のための学校を作り自立した女性を輩出していこうとしました。これは、それまでの日本になかった新たな価値を広げていったということです。越境することによって新たな世界を作り出したということでもあります。
いつの時代にもこのような越境者が新たな価値観を広げ、世界をつなぎ、新しい景色を見せてくれます。これはまさに本校の「世界をつなぐ越境者」の一つの姿です。
もう一つは、「巻き込む力」の重要性です。梅子の二度目の留学は多くの人の助けを借りて実現しています。自らの理想や熱意を周囲に伝え、周囲を巻きこみながら理想を叶えています。そのために、梅子は多くの人に多くの手紙で気持ちを伝えています。彼女の書いた手紙は何百通とも言われています。帰国後の学校設立にも梅子の熱意に多くの人が賛同し、彼らの協力を得て実現しています。
「巻き込む力」とは、自分ひとりの力だけでなく、周囲の人々の力を借りながら、目標を実現していく力です。ただ、お願いをするのではなく、自分の考えや思いをしっかり伝え、他者から協力したいという気持ちを引出し、一緒に動いてもらう。ただ、夢を持っているだけではだれも手をさしのべてくれません。でもそれを言葉にして伝えたり、行動で示したりすると、共感し、応援してくれる人が必ず現れてきます。これからの時代は単独で何かを成し遂げるよりも多様な人々と協力し、新しい価値を生み出していく力が求められます。皆さんも周囲に自分の思いを伝え、自分の夢や目標に向かって一緒に進んでくれる仲間を見つけ仲間を巻き込んでいってください。
津田梅子は自身の創設した学校の卒業式で学長として卒業生にこのようなメッセージを送っています。
Graduation from school may be compared to the launching of a ship that starts out to meet the test of wind and wave.
「学校を卒業するということは、荒波の中に向かう船旅の始まりのようなものです」と。
また、このようにも述べています。
You are responsible to your school and to your teachers that what has been gained by you shall not be lost.
「あなたたちには、学校や先生に対し、これまで学んだことを忘れずに今後に生かしていく責任があるのです。」という意味です。
卒業生の皆さん、皆さんはこれから日吉ケ丘高校という安心できる場所から離れ、人生の荒波に飛び込んでいくことになります。しかし日吉ケ丘高校で学んだことはその旅の大きな力になるはずです。自信をもって広い世界に飛び出し、津田梅子が切り開いた道のように、新しい価値を生み出し、未来を作り上げていってください。皆さんの船出を応援しています。
最後に、高いところからではございますが、保護者の皆様に一言御挨拶を申し上げます。
本日はお子様の御卒業、誠におめでとうございます。高校生活を通して、お子様は立派に成長されました。これから一人の大人として、自分の意志で社会を歩んでいくお子様を、引き続き温かく見守っていただきたく存じます。また、この3年間、様々に御支援と御協力を賜りましたことに、厚く御礼申し上げます。
卒業生の皆さん、明日からは、この日吉ケ丘高校が母校となります。いつの日か皆さんそれぞれの「世界をつなぐ越境者」として成長した姿を、見せてくれることを期待いたしまして、式辞といたします。
令和7年2月28日
京都市立日吉ケ丘高等学校長
太山 陽子