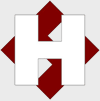
-
すべては君の「知りたい」からはじまる
堀川高等学校
普通科・探究学科群(人間探究科・自然探究科)
〒604-8254 京都市中京区東堀川通錦小路上ル四坊堀川町622-2[MAPを見る]
TEL. 075-211-5351 FAX. 075-211-8975
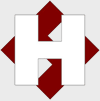
すべては君の「知りたい」からはじまる
普通科・探究学科群(人間探究科・自然探究科)
〒604-8254 京都市中京区東堀川通錦小路上ル四坊堀川町622-2[MAPを見る]
TEL. 075-211-5351 FAX. 075-211-8975
春の街に薫風が吹き抜ける今日、令和7年度入学式を挙行いたしました。
京都市教育委員会指導主事・中村央志様、堀川同窓会長・門川大作様、堀川教育財団理事長・仁科繁一様、学校運営協議会理事長・森里龍生様、PTA会長・岩崎保之様、学校運営協議会委員・松崎真后様はじめ、関係の皆さまのご臨席を賜り、ありがとうございます。また、保護者の皆様にも数多くご出席いただきましたことを深く感謝いたします。
式辞の一部(抜粋)を、以下ご紹介いたします。
新入生諸君、入学にあたり3つの話をしたいと思います。
まず、1つ目、校訓について。堀川高校の校訓は、「立志・勉励・自主・友愛」。本校では、校訓の意味するところが、学ぶ者としての姿勢であると考えています。校訓の意味を日常の学校生活の中に生かし、具現化していってほしいと願っています。この校訓の延長線上に、何があるのでしょうか。私たちは、何のために学校に通い、何のために学び、何のために働くのでしょうか。それは、自分だけが高い目標を掲げ、自分のためだけに勉学に励み、自分のためだけに批判的な観点を養い、ごく身近な人とだけ融和することを意味するのでしょうか。高校生活において、次のステージへ向けて新たな挑戦が始まります。しかし、新たな挑戦とは、大学進学という次の目標に向けての努力のことだけを指してはいません。さきほど「二兎を追う」と言いましたが、勉強と探究活動を、自分のためだけに取り組むことを意味してはいません。「立志・勉励・自主・友愛」この姿勢を持ち、高校生活を過ごしていく中でのヒントとして「他者性」という言葉を皆さんに示唆しておきます。自らとは異なる存在としての他者を他者として認めつつ、相互承認する。自分のためだけでなく、他者のために思考し、言葉を紡ぎ、そして行動する。自分と、また他者と向き合い、ものごとに真正面から挑戦し、成長していこう。
次に、2つ目、私たちが生きる世界について。世界情勢は混迷を極めており、いま、この時間においても、世界各地では争いが続き、貧困にあえぐ人々が数えきれないほど存在しています。 悲しみや憎しみの連鎖には、いつ終わりが来るのか。その連鎖を、誰が断ち切るのか。そもそも、なぜ悲惨な諍いや各地での紛争につながる、怨嗟や憎悪が生み出されるのか。一人ひとりの存在は掛け替えのないものであり、他者の尊厳は公正かつ公平にたっとばなければなりません。この一点こそが、自分にとっても他者にとっても、豊かな社会を現実のものにするための出発点であろうと思います。人間はこれまで、筆舌に尽くしがたい困難な状況にあっても、常に未来に向かって生きてきました。多難を理由に問題から目をそむけ、無関心でいることなく、状況に向き合う。艱難辛苦を一つずつ克服する。それは私たちに課せられた使命であり責任です。
最後に3つ目。27期生の皆さんに、一つのテーマを提示します。
「一灯(いっとう)をさげて暗夜(あんや)を行く。暗夜(あんや)を憂うなかれ、一灯を頼め。」江戸時代の儒学者・佐藤一斎(さとう いっさい)の格言です。「一張(ひとはり)の提灯(ちょうちん)を下げていれば暗い夜道も暗い闇も怖がることはない。ただ自分の足元を照らすその一つの灯りを頼りにして、前に歩き進めばよい」ということを表現しています。ともしび=灯(あかり)は、たとえどんなに小さなものであったとしても、足元を照らし、力強い支えとなる。灯り(あかり)の下(もと)に自分も他者も集まる。仲間とともに、力を合わせ、時として生じる対立や摩擦を恐れず、臆することなく渦中に飛び込む。対話を通してジレンマを乗り越え、粘り強く合意形成し、次へ向けて歩を進める。灯り(あかり)は過去を映し出し、現状を炙り出し、足元を照らし、灯火として仲間が離合集散する象徴となり、やがて、未来への光明をもたらす。
27期生の皆さんには、「灯(あかり)」という言葉を捧げます。
今は小さなともしびも、やがて未来の希望となる。
新入生諸君、あらためて、ようこそ堀川高校へ。
この堀川高校で、家族以外で最も身近な他者となる仲間とともに、多くの経験を重ね、新たな挑戦を続けていこう。それぞれの「灯(あかり)」を持ち寄りながら。
令和7年4月8日
京都市立堀川高等学校
校長 船越 康平