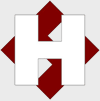
-
すべては君の「知りたい」からはじまる
堀川高等学校
普通科・探究学科群(人間探究科・自然探究科)
〒604-8254 京都市中京区東堀川通錦小路上ル四坊堀川町622-2[MAPを見る]
TEL. 075-211-5351 FAX. 075-211-8975
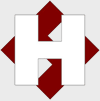
すべては君の「知りたい」からはじまる
普通科・探究学科群(人間探究科・自然探究科)
〒604-8254 京都市中京区東堀川通錦小路上ル四坊堀川町622-2[MAPを見る]
TEL. 075-211-5351 FAX. 075-211-8975
7月29日(火)、京都大学文学部長の出口康夫先生を講師としてお招きし、『WEターンからAI親友論へ+エッセイの書き方京大哲学流』を演題にご講演いただきました。
1年生の夏の探究テーマの一覧を見ていただき面白そうだと思ったという嬉しいお言葉をいただき、その上で、高校、大学は学問の基礎段階であり、その段階で基礎的な知的体力をつけることが重要だとお話しされました。その際、スポーツによってトレーニングが異なるのと同様、なりたい自分(10年後)のイメージを持って、それに基づく知識をつけるという「backwardな考え方」が重要になると教えていただきました。また、なりたい自分がすぐになくても、「持とうとすること」、「ここなら任せろという狭い入口を決めてそこから知識を広げていくこと」が大切だとお話しされました。
続いて、大学生や院生にも伝えておられる論文の書き方を紹介されました。「最初に一文で問いを」「最後に一文で答えを」「間は問いから答えに至る必要要素をすべて入れ、不必要要素は全て排す」これをポイントにしながらも、研究では答えが見えず、問いに戻ることの繰り返しになること、そのため「シンプル」「答えられる」「答えられるけど(矮小化せず)大きな問いと結びつける」「(専門家でも)考えたこともなかった」という要素をヒントに、「面白い」問いを立てることが重要だと教えていただきました。
そののち、学問の一分野として、ご専門の哲学においてご自身が提唱される「WEターン」の考え方をご講義いただきました。これはIからWEへ視点を変えることであり、私たちの行為の全ての主体はIではなくWeだとする考え方です。太古の時代のシアノバクテリアや周囲の植物の存在によって酸素を吸うという行為が可能であること、道路、自転車、信号機、交通ルールがあるからこそ、私が自転車に乗るという行為が可能であることなどを例に、単独行為というのは不可能であることをご説明いただきました。また、Weにも「悪いWe(中心占有的、真ん中にWeを据える)」と「良いWe(中空的、あえて真ん中を空ける)」があり、知性のある人間や命のある動植物などを中心に据えるWeではなく、人工物も含め全てが主体、権利、責任を有するという考え方に、転換していくことの重要性を教えていただきました。
また、先生のお考えを聞いた上で、例えば「人工物であるAIとの関係をどう築くか」「人間として行為をしているものは一体何なのか」「自由とは何か」などの問いが立てられること、それらの問いには答えに至る様々な構造を持ちうることなどをお話しされ、具体的に新しいことを知ることが、問いを立てることにつながる、という、1年生の探究の展開に大きなヒントになるメッセージをいただきました。
講演後の質疑応答では、「IからWEへの広がりという視点と捉えたが、ターンという言葉を使われているのはなぜか」という生徒からの質問に対して、「20世紀にハイデガーにより「生」ではなく「死」から人生を考えるというターンがあったのに対し、今はどのようなターンがあるかというインタビューに答えた際に、思いついた言葉であり、君の捉え方は正しいです。Iオンリーの視点ではなくIとWEへのターンと言えますね。」と丁寧にお答えいただきました。生徒の一人は、講演後、「WEターンでは人工物もWEに含まれるというのは分かった気がするけど、それが具体的にどういうことになるのか考えるのが難しい」と話してくれました。
さらに、講演会後には、座談会の時間を取っていただき、「We」という集団の中に中心的(絶対的)力を握る存在がいない中空構造になると、リーダーがいないから、そもそもの構造が崩れるのではないか、「I」を考えるときに、細胞などもそれぞれ独立したものだと考えたら、それは「I」が「We」であることになるのではないか、など参加した生徒それぞれが直接先生に質問し、30分の想定を大きく超え、1時間以上もご対応いただきました。また、先生が大学学部生のときに使われたボロボロのペーパーバックとハードカバーのカントの原書と、それを翻訳し一行一行のつながりや論理をまとめられた書類の束を見せていただきました。生徒は興味津々でのぞき込み、驚きと感動の表情でしたが、講演の冒頭でお話しいただいた、高校・大学時代はここなら任せろという狭い入口を決めてそこから知識を広げ、知的体力をつけていくこと、その営みの中で自分をごまかさずやったと言える自信こそが、非常に重要になることを、先生のご経験を通して実感する、本当に貴重な機会になったと思います。
出口先生、本日は本当にありがとうございました。

