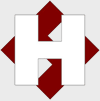
-
すべては君の「知りたい」からはじまる
堀川高等学校
普通科・探究学科群(人間探究科・自然探究科)
〒604-8254 京都市中京区東堀川通錦小路上ル四坊堀川町622-2[MAPを見る]
TEL. 075-211-5351 FAX. 075-211-8975
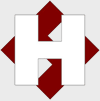
すべては君の「知りたい」からはじまる
普通科・探究学科群(人間探究科・自然探究科)
〒604-8254 京都市中京区東堀川通錦小路上ル四坊堀川町622-2[MAPを見る]
TEL. 075-211-5351 FAX. 075-211-8975
11月7日(金)、本校において第27回教育研究大会を開催しました。本校の教育活動の実践を報告し、教育関係者の方々から本校の教育活動に対して多面的な評価を受け、活発に交流する機会とするため、毎年開催しています。今回は「適切な自己評価、自己分析をし、行動に移すことができる生徒の育成」を研究テーマとし、全国から140名の教育関係者のみなさまにご参加いただきました。本当にありがとうございました。
大会は、京都市教育委員会指導部担当部長である菅野明宏様からのご挨拶で始まり、船越学校長からは「変革を恐れず挑戦する」との話がありました。続いて、京都大学大学院教育学研究科教授の西岡加名恵様から、「自ら学ぶ力をどう育てるか?―パフォーマンス評価の視点から―」と題して、本来育てるべき「主体性」の分類や、パフォーマンス課題の作り方などについて、西岡先生が様々な学校で見てこられた実践や、そこでどのような生徒の行動変容が起こっているか、などについて、基調講演をいただきました。その上で、令和4年度からの1年次から3年次にかけて段階的に授業時数を減じていく教育課程で学年主任を務めた本校の飯島弘一郎研究部長より、教育課程のねらいや、具体的な教育実践についてご報告するとともに、特に教科指導において、行動変容を促す働きかけの在り方を参加者と交流したいとの思いが伝えられました。
その後、会場を教室や特別教室へ移し、研究授業として、言語文化、歴史総合、数学研究1、地学基礎、英語コミュニケーション2の各授業をみていただくとともに、公開授業として、日々の各教科の授業実践の様子を見学していただきました。
午後からは、各教科別の分科会を行い、参加者とともに活発な質疑応答・意見交流が行われました。参加者のみなさまからは、「行動が変容したことをどのように見とるのか」「自ら学ぶことを可能にするために、授業内でどこまでの補助が必要になるかには各校の差があり、その見極めが重要」「学年を越えて生徒が学ぶことができる余白の時間もあり得る」など、多くのご意見をいただきました。福島、福岡など全国の高等学校の先生方や、海外で日本の教育について研究されている研究者の方々などと、「余白」での行動変容をうながす教育活動について議論する大変貴重な時間となりました。
最後に講堂にて全体会2として、飯島研究部長と濱田第1学年主任より、1年次に設定している「学びのアセスメント」の時間に関する取組内容を中心に、ご報告いたしました。また、西岡加名恵教授からは、見ていただいた5つの研究授業について、即座に、授業や生徒の様子について、本当に詳細なフィードバックをいただき、長期的な目標を掲げた上での授業計画や、授業者が発する問いの重要性など、改めて日々の授業実践を向上させる上での様々な視点を学ぶことができました。
本日ご参加のすべてのみなさまから、たくさんのご意見・ご助言をいただきました。今後の取組に活かしていきたいと思っております。本日はご多忙の中、ご参加いただき、ありがとうございました。

