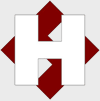
-
すべては君の「知りたい」からはじまる
堀川高等学校
普通科・探究学科群(人間探究科・自然探究科)
〒604-8254 京都市中京区東堀川通錦小路上ル四坊堀川町622-2[MAPを見る]
TEL. 075-211-5351 FAX. 075-211-8975
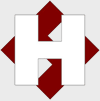
すべては君の「知りたい」からはじまる
普通科・探究学科群(人間探究科・自然探究科)
〒604-8254 京都市中京区東堀川通錦小路上ル四坊堀川町622-2[MAPを見る]
TEL. 075-211-5351 FAX. 075-211-8975
2日目。この事前学習のメインテーマの一つである、震災によって甚大な被害を受けた石川県輪島市に視察に向かいました。
午前中、輪島市役所に到着した私たちは、輪島市役所観光課の向面(むかいづら)さんより発災時の様子や被害状況、当時の住民の思いなどご講演をいただきました。
発災時、家族と共にしていた向面さんは、ご家族を避難させた後、ご自身は当時ご勤務されていた市民病院へ赴き、次々と運ばれてくる患者さんに対応されたようです。つい先日までお会いしていた知り合いの方が、変わり果てた姿で運ばれてくる。そうした凄惨な現場で、ご自身の家族の安否も分からない中で、「心を無にして」職務を全うされる。言葉にするには難しい、本当の意味で過酷な日々と向き合った向面さんのお話は、生徒の心に強く響いたことでしょう。
ご講演後は、輪島市の中でも最も活気のあった「輪島朝市」跡に視察へ訪れました。そこにあったのは、鬱蒼と雑草の生えた、荒涼とした風景。地震発生後に起きた火災によって消失した家屋が撤去され、残された電柱は黒く焼け焦げ、傾いたまま。火災から逃れようと逃げる人、倒壊した家屋の下敷きになり、「助けて」と叫ぶ声ーーそうした阿鼻叫喚の惨状が、まるで信じられない不気味なまでの静けさに覆われた大地が、そこにはありました。付近の「キリコ会館」(キリコとは、能登半島の祭りで使用される巨大な灯篭)にて、展示されたキリコが地震により倒壊した現場も視察しました。代々に渡って受け継がれてきた想いを象徴したキリコが、無惨にも破壊されている様子は、心にくるものがありました。
午後は場所を移し、「のとじま水族館」へ。震災の被害は、住宅だけではなく、当然の如く観光施設にも広がっていました。特に生き物を扱う水族館では、地震によって破損した水道管や、なかなか復旧しない上下水道が、飼育する生き物の命に直結してしまうことから、飼育員さんをはじめ多くの人が尽力された様子が、パネル展示されていました。また、全国の水族館が一時的に生き物を引き取って、何とか通常営業に漕ぎつけようと努力された姿も、パネル越しに伝わってきました。
最後に、向面さんのご講演で印象に残った言葉から一つ。遠く離れた私たちにできることは、「忘れないで」いてほしい、そして「勇気づけて」ほしい。欲しいのは物的支援ではなく、「気持ち」であると。終わりの見えない復旧・復興に向けての一歩を踏み出していく彼らを支えていくために、この経験を、友達や家族に伝え、決して過去の出来事として風化させないこと。これが私たちに科された使命だと思います。是非、京都に戻った後、この経験を様々な人に語り伝えていって欲しいと強く願います。

