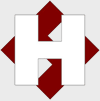
-
すべては君の「知りたい」からはじまる
堀川高等学校
普通科・探究学科群(人間探究科・自然探究科)
〒604-8254 京都市中京区東堀川通錦小路上ル四坊堀川町622-2[MAPを見る]
TEL. 075-211-5351 FAX. 075-211-8975
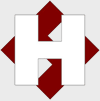
すべては君の「知りたい」からはじまる
普通科・探究学科群(人間探究科・自然探究科)
〒604-8254 京都市中京区東堀川通錦小路上ル四坊堀川町622-2[MAPを見る]
TEL. 075-211-5351 FAX. 075-211-8975
3日目。2泊3日の事前学習もいよいよ最終日となりました。本日は金沢大学人間社会研究地域創造学系の青木賢斗(あおきたつと)准教授より、能登半島地震のメカニズムおよび、能登という地理的条件が復旧に向けて与える影響など、学術的見地からご講演をいただきました。
地震のメカニズムについては、日本列島の地形形成史という大きなスケールからその要因を解説していただきました。能登半島では輪島市で最大4mほどの隆起が起こりましたが、これは能登半島を挟むように断層が位置しており、こんにゃくゼリーのカップを両側からつまむような力が加わったなど、生徒にとってイメージしやすく説明していただきました。
また、地震と聞くと地震=災害=悪と捉えられがちではあるけれども、実は過去に起きた地震によって生じた地殻変動が、人々の暮らしにも活かされているというお話も伺いました。能登で有名な揚浜式の塩田は、地震によって地面が隆起して形成された海岸段丘の段丘面を活用していたり、能登の伝統産業である七輪で使用される珪藻土も、この隆起によって海底面に堆積した地層が陸上で採掘することができたために産業として成立していたり、地滑りによって生じた緩斜面を水田として利用していたり…時間的スケールを変えることで地震という自然現象が、人間にとって災害にも恩恵にもなるという、自然と人間の相互依存関係というものをわかりやすく説明してくださりました。
しかし、緩斜面が形成され、水田に利用されることにより能登半島の各地で定住が進み、小規模な集落が成立したことで、災害復旧時にそういった集落の支援が困難となる要因になってしまっているということもあるそうで、地震の恩恵により得られた人々の生活が、自身の被害を拡大させることもあるのだと、私自身も感心させられました。
青木先生によれば、石川県は大きな地震の被害が過去にあまり多くないことから、あまり地震に対する防災意識というのは高いとは言えないと仰っていました。京都に住む私たちも同じではないでしょうか。地震の被害が直撃することがあまり多くない京都に暮らす私たちも、その危険性は分かっていても、いざ起きた時にどう行動するか、そこまでシュミレーションしている人は少ないように思います。「備えあれば憂いなし」と言いますが、まずは自分たちの住んでいる地域にどのような地形的特徴があり、どのような災害リスクが把握すること、そしていざ発災したときの行動指針を考えておくこと、「備えあって、憂う」姿勢が大切なのだと再認識させられました。
この2泊3日、多角的な観点から「能登半島地震」について学びを深めることができました。大事なのは、これを客観的事象として捉えるのではなく、同じ日本に暮らしている人間として、当事者意識を持つことだと思います。災害の被害を少しでも小さくするために、私たちの暮らしている地域がどのような地形で、どのようなリスクが存在するのか、そして発災した時にどのような行動を取るべきなのかシュミレーションしておくことが必要だと痛感しました。

