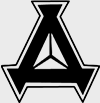
-
一歩踏み出すGlobal Citizen
紫野高等学校
普通科・アカデミア科
〒603-8231 京都市北区紫野大徳寺町22[MAPを見る]
TEL. 075-491-0221 FAX. 075-492-0968
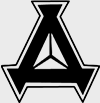
一歩踏み出すGlobal Citizen
普通科・アカデミア科
〒603-8231 京都市北区紫野大徳寺町22[MAPを見る]
TEL. 075-491-0221 FAX. 075-492-0968
「一歩踏み出すGlobal Citizen」を体現する生徒の活躍を紹介する校長室インタビュー、今回は3年7組藥師寺美丹さん(京都聖母学院中出身)です!
――drawback…、難しいな…。
藥 何読んでるんですか?
――藥師寺さんの論文だよ。ごめんお待たせ、すごいね、話は少し聞いてるけど!
藥 じゃあ、その件から説明させてもらいますね。スタンフォード大学のSPICE(国際異文化教育プログラム)が提供するE-JAPANプログラムというオンラインコースを友人から教えてもらって、おもしろそうだなと思ってやってみたんです。日本人の高校生30人が半年間、週替わりで日米文化について学ぶんです。
――全国で30人? じゃあ、選考があったの? 期間は?
藥 はい。エッセイの課題が出されて、「日米関係と私」というテーマでした。昨年の8月に出願して、夏休み明けに合格のお知らせが来て、10月くらいから今年の2月まで。最初に研究者や有識者の講義を視聴して、それからディスカッション・ボードというサイトで参加者とオンラインで議論して、週末にZoomミーティングして、レポートを書くんです。
第1回のテーマは第二次世界大戦で、日米両国にとっての原爆と真珠湾攻撃を取り上げて、中立な学びを志向するというもので、東大の教授が英語で講義してくれました。ハワイの先住民にとっては、望まないアメリカの軍事施設が置かれていたんだとか、日米両国という意識からこぼれ落ちがちな視点についても触れられていました。
――濃い学びだね! それと学校の勉強の両立は大変だったんじゃない?
藥 はい、結構大変でした(笑)。週末レポートはなんとかなるんですが、むしろディスカッション・ボードが3回投稿するルールになっていて、30人×3で週に90本読まなきゃいけなくて…。私もときどき長くなっちゃったから、あまり言えないですけど、毎回すごく長いのを書いてくる子もいて(笑)。
――ほかにはどんなテーマがあったの?
藥 日系アメリカ人の強制収容の回もあって、スタンフォードの近くのJapan Townの関係者が講師でした。じつは私、知らなくて、すごく驚いて。日系人がサボタージュやスパイをしているというあらぬ疑いをかけられて、強制的に移住させられたんですよね? 当時のアメリカにはイタリア系もドイツ系もいたけど、やっぱり日系ばかり特に差別されたそうです。
――同じ敵国でも、人種でちがったんだね。半年間のコースを終えての感想は?
藥 英語は結構ハイレベルで、私は家庭でも英語を話すけど、それでもかなり難しく感じることもありました。でも、すごく刺激を得られたし、30人のなかには親が国際結婚とか帰国子女とかじゃなくて、日本でずっと育った生徒もいたし、紫野は英語が大好きで得意な生徒が多いから、ほかにも参加する生徒が出てきたらいいなって思います。
bilingualとは少し違うbiculturalという視点について学んだんですけど、このプログラムを通して、double insider outsider perspectiveという概念が一番強く印象に残ったんです。
――それはどんなものなの?
藥 母国を飛び出して異国で暮らすと、最初はアウトサイダーとして異文化を眺めながら、徐々にそこを自分のすみかにしていく。その経験を得て母国に帰ると、今度は自分がその中に浸かっていた自文化をアウトサイダーの目で眺められるようになるという話です。
――あなた自身、日本とカナダにルーツを持っているんだよね。生まれも育ちもずっと日本なの?
藥 はい。夏休みはカナダの大好きな祖母の家で過ごしたりするんですが、例えばカナダでは、父が道端で初めて出会った人と、野球のことで延々とおしゃべりを続けたりするんです。日本では、初対面の人と路上でそんなことしませんよね。そんなとき、double insider outsider perspectiveについて実感します。
――おもしろいね。それで、この論文「DUAL CITIZENSHIP IN JAPAN」に繋がっていくんだね。日本では、20歳に達したら一方の国籍を選択しなければならないけど、トータルで考えると本人にとっても国にとっても二重国籍を認めるほうがよいという論考だね。これ、英語だとcitizenshipとnationalityという2単語が出てくるけど…。
藥 日本語だと、どちらも「国籍」ってことですよね? citizenshipは法的な意味での国籍で、nationalityは帰属意識に関するものだと思います。今回は法的な「国籍」を論じるべきと思ったので、citizenshipという語を使って論を展開するように意識しました。
――なるほど。この論文が、コースの最終課題だったんだね。
藥 はい。その中から優秀者が3名、今年の夏にスタンフォード大学に招待してもらえるんですが…、私、選ばれました!
――それは本当にすごいよ! でも、トランプ政権になって、留学生排除を大学に強硬に求め始めたから、ちょっと困ったことになったんだって?
藥 はい…。家族も私自身も、アメリカのそんな現状に疑問と不安を感じて、行くのを断念したんです…。残りの2人は行くみたい。現地で論文の発表ができることになっていて、行けない私も発表動画を撮って、ちょうど送ったところなんです。
――残念だよね…。でも、優秀者に選ばれたことは、スタンフォード大の入学選考にも繋がっていくんじゃないの?
藥 考慮はしてもらえます。でも、トランプ政権の外交政策でカナダもひどい目に遭っていますし、アメリカの大学への進学は心情的にも今は考えられないかな。日本の大学に進学して、交換留学で海外の大学に行きたいと思っています。
――そうか。それにしても、今回のコースではいい経験をしたね。
藥 グループで研究発表もしたんですよ! 私たちのグループは日本の空き家問題の解決策を発表したんです。
――え! そんなことまで。人口減少で空き家問題も深刻化してるもんね。
藥 はい。それで、地域によって課題やニーズを分類して、都心部では「グリーンスペースに開発して、緑を少しでも増やすことで住民の健康やハピネスが増進するようにする」、郊外の通勤圏では「仕事や会議のできるシェアオフィスにして、都心部への長い通勤や家ではリモートワークに集中できないなどの問題を解消する」、地方では「レンタルコテージにして、旅行に来る人に安価なスペースを提供し、現地の人にそこを管理する雇用を創出することでまちを活性化する」という3つの解決策を提案したんです。
――よく考えられているね! ところで将来はどんなことを学びたいの? 最終論文のテーマのようなことを、自分のライフワークと捉えてるの? 法学部とか?
藥 じつは生物や生命に興味があるんです。自然現象について考えるのも好きだし、環境保全や種の多様性の維持に関わることをしたいなと思ってます。
――さすが、明確だね。あなたの論文についてももっと話を聞きたかったんだけど…。残念なことに、今まさに世界中で逆風が吹いているよね。トランプ政権の話が出たけど、異質なものを排除して自国ファーストを掲げることが、どの国でももてはやされる。それはさきの参院選でもね…。
藥 そう! すごく心配です。
――それに対して、あなたが論文で示した価値観は、まさにアメリカの大学も守ろうとしているものだよね。スタンフォードはE-JAPANのようなプログラムを、恐らくいろんな国に提供しているんだろう。こんな時代だからこそ、culturally diverseでopen-mindedでinternational individualであることを理想として、multiculturalismを目指そうというあなたの主張は、本校の教育目標にもぴったりだし、とても共感しました。また話を聞かせてください!
藥 はい、これからも、この軸はブレないようにしていきたいです!
※記事及び写真は生徒本人の了承を得て掲載しています。

